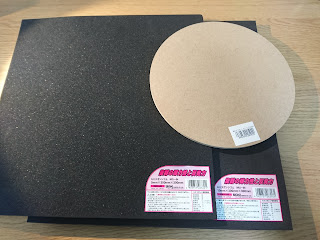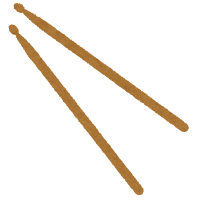打楽器基礎の練習曲を作りました【ルーディメンツとクローズドロール】

こんにちは、田畑洸貴です。 ここ数ヶ月は主に音楽指導が中心になっています。 打楽器の基礎に立ち返って教えるということは、とても良い経験になっていると思います。 基礎練習をするときに、ただ短いフレーズを練習していても面白くないので、8小節ほどの練習曲を作ることにしました。 そこで作ったものを、皆さんにも共有です。 クローズドロールの練習曲 5つ打ち/パラディドゥル/フラムの練習曲 この2曲を用意しました。 5つ打ち〜のほうは、ドラムマーチをベースにダブルストロークを活用したルーディメンツをベースにしています。 クローズドロールのほうは、ダブルストロークとクローズドロールの使い分けを目的に作ってみました。 以下の画像を保存してもらって、印刷してご活用ください! ついでに良ければ、SNSのフォロー、YouTubeチャンネルの登録もよろしくお願いします 。 訂正:クローズドロールの練習曲画像が正しく表示されておりませんでした。新しくアップしました。 田畑洸貴のSNSもフォロー宜しくお願いします! YouTube https://www.youtube.com/channel/UC6-C0BDkPPmvwn8RM5MqCow Twitter https://twitter.com/Percussion_TBT Facebook https://www.facebook.com/kouki.tabata.104